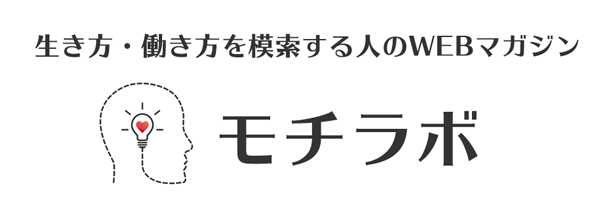ニーチェのルサンチマンとは
〜弱者のねたみと歯ぎしり

『ルサンチマン』とは、フランス語で弱者が強者に対して「うらみ・ねたみ・そねみ」といった感情を持つことを言います。
ドイツの哲学者ニーチェによれば、ルサンチマンにはそうした感情からくる復讐心を含んだ「価値の転換」といった心の動きまで含んでいるといいます。
例えば、ニーチェは下記のような出来事の背景にもルサンチマンを見出しました。
ローマ帝国時代に、ユダヤ人がそれまでの貴族的価値観をひっくり返し、「みじめな者のみが良い者である。貧しい者、力のない者のみが良い者である」というキリスト教的価値観への価値の転換をはかった……。
ユダヤ人は貧しさにあえぎつつ、権力と富をもつローマ人や王族を憎んだ。しかし現実において彼らに勝つことはできない。そこで彼らは復讐のために神をつくり出した。「あいつらにはかなわない。私たちは苦しめられている。でも、天国に行けるのは私たち貧しい者のほうだ。富者や権力者は悪人であり地獄に落ちるのだから」と。神を用いることで現実の強弱を反転させ「心理的な復讐」を果たすことができる。自分が気持ちよくなって自己肯定するのではなく、強い他者を否定することで自己肯定する。
(NHK「100分de名著」ブックス ニーチェ ツァラトゥストラ/西研)
ルサンチマンとは、こうした一連の心の動きのことです。
目次
ルサンチマンは今もいたる所で起きている
ルサンチマンは、時代を問わず見られる光景です。
「お金さえあれば自分だって」「どうせ私は可愛くない」「どうして自分ばかりこんな不幸な目に会うの」 ……そう思ったことは誰にだって一度はあるはずです。
そしてなんだか輝いて見える人に対して、「あいつは恵まれてる」「なんであいつばっかり」と「ねたみ・そねみ」を抱いたこともあるでしょう。
そんな時、あなたの中のルサンチマンが発動して次のように言わせるかもしれません。
「恵まれてるアイツは自分のことばかり考えてて嫌なやつだ。それに引き換え、私は恵まれない境遇の中で一生懸命頑張ってる……」
成功者や有名人のスキャンダルや不祥事に、ネットやテレビが過剰に反応するのも、多くの人の心の中のルサンチマンがその復讐を果たそうとしていると言っても過言ではないでしょう。
心の歯ぎしり
ルサンチマンの根っこにあるのは、弱者のねたみであり、そこからくる歯ぎしりです。
それを何かにぶつけて紛らわそうとする心の動きがルサンチマンです。
ルサンチマンを持つ人は劣等感を抱え、自分を弱者だと感じ、フラストレーションを溜めた状態にあります。
しかし、そのフラストレーションを解消するために行動を起こして現実を変えることは困難だと感じているのです。
そこでルサンチマンは、フラストレーションをむしろ肯定し、強者を攻撃することで弱者である自己を正当化しようとします。
社会的な価値観を否定したり、反転した解釈を行うようになります。
言いたいことは「自分は間違っていない。間違っているのはあいつらだ」ということです。これを主張するために論理をこねくり回します。
自分を腐らせるルサンチマン
誰の心の中にもあるルサンチマンですが、問題はそこに入り込んでずっととどまっていると自分自身を腐らせてしまうことです。
ルサンチマンの論理では、強者は"悪"で弱者の自分こそ"善"ですから、現実に努力して何かを達成しようとする意志が奪われてしまいます。
やがて成功するために努力することすら悪になり、弱者にとどまることこそ善だということになっていき、周囲の人に対してもなんとかそこにとどまらせようとするのです。
ルサンチマンは、繰り返し「弱者こそ正しいのだ」とあなたの中にある「怠け心・諦めの心」を通して囁きます。
「これからもここで生きていこう。それこそが正しい道だし、元々あなたは犠牲者で悪いのはあいつらだ。私には不平不満を言う権利がある」というわけです。
また、ルサンチマンの論理では、自分が善であるためには、敵を想定して、その対象者が悪でなくてはなりません。
なぜなら、その敵こそが悪の元凶であって、その対比として自分が善だからです。
だから、それを証明するために躍起になります。
重箱の隅をつついても、あら探しをしてでも対象者が悪であることを証明しなくてはならないと感じるわけです。
こうして、いつの間にか現実をよくするための努力ではなくルサンチマンの論理を強化するために努力するようになっていきます。
ルサンチマンとは「ブーたれ」ですから、自分から動く能動性を失わせてしまい、「文句をいう」という微弱な快感とひきかえに、積極的に悦びを汲み取ろうとする力を損ねてしまうのです。
(NHK「100分de名著」ブックス ニーチェ ツァラトゥストラ/西研)
結局、ルサンチマンを抱えたまま生きる人生はどこか息苦しく暗い感じで、爽やかさがありません。
ルサンチマンのことを奴隷精神と呼ぶこともありますが、それは自分で自分をどこか暗い牢屋のような所に閉じ込めておくようなものだからなのかもしれません。
ルサンチマンに飲み込まれないために

強者に対して「うらみ・ねたみ・そねみ」といった複雑な感情を抱くのは仕方ありません。人間ですからそうした感情だって芽生えて当然です。
繰り返しますが、ルサンチマンは誰の心にも存在します。
そのこと自体は否定されるものではありません。
むしろ、その後の心の中の論理展開にこそ注意が必要です。
自分の中に芽生えた劣等感や葛藤といった感情を、どこにぶつけていくのかということです。
ここでルサンチマンに入り込まず(入ってもそこにずっととどまることなく)、建設的な道を選択できるかどうかがその人の生き方を左右します。
建設的な道とは、自立的で前向きでポジティブな道です。
今足りないもの、不足しているものに目を向けて生きるのではなく、今自分にあるものから生きていく姿勢です。
「三人称」(どこかの誰か)が主語になり、「〜できない」「〜せざるを得ない」という姿勢ではなく、「私」が主語になり「〜したい」「〜してみよう」という姿勢です。
もし自分とは直接関係のない有名人か誰かに必要以上の怒りが湧いてくるようなら、もしかしたらあなたの中のルサンチマンが声を上げているのかもしれません。
そんな時は「あぁ〜、また怒ってる。私はなんて嫌なやつなんだ」とはならずに、「大丈夫、大丈夫」と静かに自分に言い聞かせてあげてください。
たとえば、美しいまっさらのキャンバスがあって、そこに自在に絵を描いていけるなら「ゼロからのスタート」ですから気持ちがよいでしょうが、じっさいはそんなことはない。人はみな、しみがあったりデコボコになったりしているキャンバスのもとで生きていくしかない。しかも、人によってかなりちがいがある。しみが目立たないキレイなキャンバスに恵まれた人もいれば、巨大なしみだらけのものもある。しかしそれはもう「定まったもの」である。このしみだらけでデコボコのキャンバスに文句をつけるのではなく、その上にどうやって自分なりの絵を描くか、それはあなた自身に委ねられている。
(NHK「100分de名著」ブックス ニーチェ ツァラトゥストラ/西研)
まとめ
ルサンチマンとは、弱者が強者に対して「うらみ・ねたみ・そねみ」といった感情を持つことでした。
ルサンチマンは都合の良い論理展開で自己を正当化することで、その人を精神的に腐らせてしまいます。
奴隷精神に飲み込まれ、人生をブーたれながら生きていくことになってしまいます。
案外、誰もが知らぬ間に飲み込まれてしまう心理状態であり、いつの時代でも注意が必要です。

ルサンチマンって何だかヒーローみたいな名前だけど真逆だね。
 このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。
このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。
→もっと見る | 仕事依頼
Follow
メールマガジン
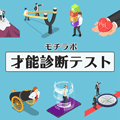 才能診断テスト
才能診断テスト
あなたの才能が「見える化」される。全世界で2000万人以上が受けた才能診断ツールをベースにした本格派。 私の本が出版されました!!
私の本が出版されました!!
9割の人は自分の”心の使い方”を知らないために人生損しています。