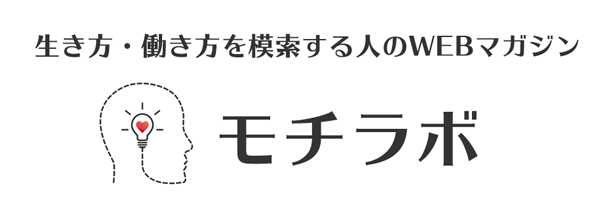空虚感とは何か?

空虚感(くうきょかん)とは、心にぽっかり穴が空いたような、虚しくて空っぽな感じの心の状態のことです。
何か大事にしていたものを失った時にそうした空虚感に襲われることもありますし、特に何かがあったわけでなくとも、ふと突然空虚感に苛まれることもあります。
そうなってしまうと、何をするのも虚しく無意味に感じられ、なかなか気力が湧いてきません。
出てくるのはため息ばかりで、長い間そこから抜け出せずにいると人生を大きく損なってしまう恐れもあります。
つまり、空虚感とは「生きていく上で最も大切な何か」「原動力のようなもの」が失われている状態とも言えるでしょう。
そして、もしかしたらその「大切な何か」とは、意味や意義、生きがいなどといったものなのかも知れません。
効率化などによって社会全体は驚くほど便利になりました。
しかし、その裏で人間同士は深いつながりを失い、多くの仕事は単なる労働へと変わってしまいました。
また、SNSなどの普及によって私たちはよりたくさんの人たちと繋がることができるようになりました。
しかし、逆に生身の人間同士の深い繋がりを感じる機会は減ってしまいました。
そんな中に生きる私たちは、魂の渇き、そしてその現れとしての空虚感に苛まれやすい環境で生きているといっても過言ではないではないでしょう。
目次
空虚感を生み出す3つの原因
心理学者のフランクルは、多くの人が生きる意味や生きがいを喪失した状態に苦しんでいると述べ、そのような人間の状態を「実存的空虚」と呼びました。
フランクルいわく、人々が生きがいを喪失した原因は三つあると言います。
①人間は動物と違い人生に主体的な意味を見出したいという根源的願いを持っているためその問題に向き合わざるを得ない。
②古い道徳や伝統的価値観が崩れてしまったため、今は何を拠り所に行動して良いのか、あてどもない荒野に放り出されたようで、何を欲し何をしたら良いか全くわからぬ状態に立ち至っている。
③テクノロジーや教育における間違った人間観が、本来複雑な動態である人間を、単なる一機能のように捉えて物事を推し進めてきたため、その弊害が出ている。
これらの原因によって生きがいを失い空虚感に苛まれている人は、当時(1970年前後でしょうか)のアメリカ人では60%もの人が該当したと言います(恐らくこの割合は今でも大きくは変わっていないでしょう)。
さらに、プラハの学生に至ってはそれを超える数字を示していました。
ところが、「プラハの春」と呼ばれた表現の自由などを求めた民主化運動が起こると、その比率は著しく低下したといいます。
彼らは社会的ムーブメントの中で力強く行動すべき目標、つまり生きがいを見つけた。
そして、それが実存的空虚を埋めたというわけです。
意味への意志
フランクルの話をもう少し続けます。
彼は、人間は生きている限り「この人生でなすべきことをしていると思いたい」「意味のある人生を送っていると思いたい」という欲求から解き放たれることはないと言います。
それは人間の根本的な動機であり、それを「意味への意志」と呼びました。
しかし、私たち現代人の多くは、当時のプラハの若者が持っていたこの「なんのため(意味)」をなかなか見出せない。
だから空虚感に苛まれやすいわけです。
それでも、私たちの中にある「意味への意志」は意味を求めることをやめない。
とにかくなんでもいいから空虚感を埋めようと躍起になる。
その結果、時にお金や他人への攻撃といった刺激でそれを埋めようとすることもあるでしょう。
スマホが手放せないのは、空虚感から逃れようとする魂の手が、手軽にちょっとした刺激を与えてくれるそれを掴んで離さないのかもしれません。
また、表面だけの空っぽなポジティブ思考で空虚感を埋めようとする動きも最近目立つようになりました。
言ってることは明るく前向きなのに、そうした人の言葉はどこか不自然で醸し出す雰囲気は空虚だったりします。
結局、空虚感を埋めるものは人生の意味や魂の喜びなどといった、人間の生命の根源に近いところの実感であり、何か表面的なものでそれを埋め合わせようとしてもうまくはいかないものなのでしょう。
岡本太郎の言葉
芸術家の岡本太郎は著書の中で次のように述べています。
たしかに今日の小市民生活は物質的には恵まれている。暮らしは昔に比べて遥かに楽になってはいるが、そのために生命の緊張感を失い、逆に虚しくなっている。
進歩だとか福祉だとかいって、誰もがその状況に甘えてしまっている。システムの中で安全に生活することばかり考え、危険に体当たりして生きがいを貫こうとすることは稀である。自分を大事にしようとするから、逆に生きがいを失ってしまうのだ。
惰性的に過ごせば死の危険は遠ざかる。
しかし虚しい。 死を恐れて引っ込んでしまっては、生きがいは無くなる。今日はほとんどの人が、その純粋な生と死の問題を回避してしまっている。
だから虚脱状態になっているのだ。個人財産、利害損得だけにこだわり、またひたすらにマイホームの無事安全を願う、現代人のけち臭さ。卑しい。
小市民根性を見るにつけ、こんな群れの延長である人類の運命などというものは、逆に蹴飛ばしてやりたくなる。
死ぬもよし、生きるもよし。ただし、その瞬間にベストを尽くすことだ。現在に強烈に開くべきだ。未練がましくある必要は無いのだ。
まとめ
空虚感の奥にある声は何と言っているでしょうか?
きっと「もっと意味のあることをしたい。人間として生命を燃焼したい」といった魂の叫びがそこにはあるのではないでしょうか。
もし、空虚感がいつまでたっても消えないようであれば、それは何か大きな変化が必要です。
空虚感を抱えたままずっと生きるのは、やっぱり誰だってイヤでしょう?
 このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。
このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。
→もっと見る | 仕事依頼
Follow
メールマガジン
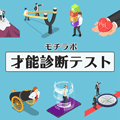 才能診断テスト
才能診断テスト
あなたの才能が「見える化」される。全世界で2000万人以上が受けた才能診断ツールをベースにした本格派。 私の本が出版されました!!
私の本が出版されました!!
9割の人は自分の”心の使い方”を知らないために人生損しています。