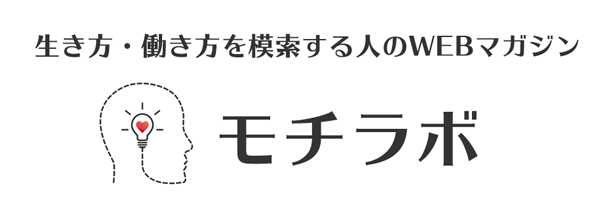「粋(いき)」という日本人特有の美意識とは?

「粋(いき)」という言葉があります。
昨今「アイツは粋な野郎だな」などという会話は、時代劇以外であまり聞くことがありません。
しかし、「粋な計らい」「粋なお店」などという言葉は今でも使われることがあります。
大抵、「気が利いていて押し付けがましくない」といった様子に対して「粋」という言葉が当てはめられています。
ここでは、この「粋」という概念について改めて考えていきます。
なぜなら「粋」という言葉には私たち日本人の美意識がギュッと詰まっているからです。
この「粋」という言葉に詰まった曖昧なニュアンスを外国人は理解できないといいます。
外国にはあまり無い概念なんだそうです。
私たち日本人は誰しもが理解している絶妙な美意識。
それが「粋」です。
ただし、近年の欧米化の流れの中で「粋」を感じるものが急速に減っているように感じます。
もしかしたら数十年後には、この「粋」という感覚はもはや日本人なら誰しもが共有する感覚では無くなってしまうのかもしれない。
そんな危機感の中、この記事を書いています。
目次
「粋(いき)」とは何か
「粋」とは、もともと江戸時代後期に江戸深川の芸者について語ったのが始まりとされています。
身なりや振る舞いが洗練されていて、色気とさっぱりとした心持ちが同居しているような芸者の様を見て、当時の人たちは「粋だね〜」と言ったのでしょう。
「粋」という概念を理解する上で忘れてはならない一冊の本があります。
大正〜昭和時代の哲学者・九鬼周造(1888〜1941年)の代表的著作「いきの構造」です。
曖昧な「いき」というものについて構造的に明らかにしようとした一冊です。
それによると、九鬼は「粋(いき)」を3つの特徴で定義しています。
1)媚態(びたい)
異性に対する「つやっぽさ」や「色気」であり、セクシーで上品な振る舞いともいえます。
2)意気地
反骨心や気概といったもの。「武士は食わねど高楊枝」といったやせ我慢や媚びない気概のようなもの。
3)諦め
運命を受け入れ、未練がましくなく、あっさりとした姿勢。無常観といった仏教的思想が反映されています。
つまり、「色気があって、気高く、さっぱりとした心持ちを持った様子」が「粋(いき)」だということになります。
もちろん、これだけで「粋」という微妙なニュアンスを持った言葉を正確に表せるわけではありません。
一般的に「粋」の反対語は「野暮」ですが、九鬼自身も先ほどの本の中でさらに他の言葉(「上品・下品」「派手・地味」「渋み・甘み」)との関係性の中から「粋」の意味を探っています。
それらのどれにも当てはまらないものが「粋」であるというわけです。
ちなみに、Googleで調べてみると次のように出てきました。
「さっぱりした気立てで、あかぬけがし、色気(いろけ)もただようこと。そういう感じのする身のこなし・様子」
私たちは「粋」が好き
さて、言葉の定義はさておき、「粋」というのは江戸の庶民の間で生まれた概念だと言われ、当時の人たちがカッコいいと考えていた美意識、生き様、価値観、美学、哲学といったものだと言えます。
その感覚は学校で習うことはないけれど、現代に生きる私たちにも脈々と受け継がれています。
だからやっぱり、私たちは「粋」と感じるものが好きなわけです。
日本人が「桜」や「紅葉」をこよなく愛するのも、きっとその儚さに「粋」を感じているからなのでしょう。
(例えば「薔薇」はもちろん綺麗ですが、粋かどうかという点では派手すぎて野暮ということになるのかもしれません)
明治になって「I love you」という英語が日本に入ってきた時、夏目漱石はそれを「月が綺麗ですね」と訳したといいますが、その話を聞くと「粋だな〜」と感じます。
露骨な表現は野暮であり、奥に秘められたものの暗示性を大切にするのも「粋」という美意識にとって大切なものなのでしょう。
しかし、冒頭に書いたように私たちを取り巻く環境の中で、粋という美意識が急速に廃れているようにも感じます。
周囲で起こる出来事を「粋」か「野暮」かに分類したら、ほとんどのことが「野暮」に分類されてしまうのではないでしょうか。
「粋」という美学を持って生きる
通常、私たちが何か物事を判断する時、それが「損か?得か?」「正しいか?間違っているか?」といった判断基準を持って行っていると思います。
きっと江戸の庶民は、それにプラスして「粋か?」「野暮か?」という判断基準を大事に暮らしていた。
もしかしたら、それは今の女子高生が「可愛いか?」「可愛くないか?」という判断基準に重きを置いているのと同じ感じなのかもしれません。
彼女たちは、大人から見ると呆れるほど「カワイイ」という価値観に重きを置いています。 そして、それを基準に様々な物事を判断しているようです。
最近、そんな女子高生や江戸の庶民と同じように、改めて「粋」という価値観を大事に生きてみるのも良いのではないかと思っています。
それはただ「得なもの」「便利なもの」に流されて生きるのではなく、自分(の価値観)に主導権を取り戻すということにつながるような気がします。
江戸の庶民と同じように、意地をはることで自尊心を守るということになるのかもしれません。
何かに負けまいと意地をはる、しかしその結果や運命には執着せず、色気や艶っぽさを大事にする。
「粋」な生き方とは、そんな感じになるでしょうか。
また、過剰な優しさや愛情表現など、もともと欧米的概念である「人間中心主義」といった価値観がいまいちシックリこない人は、「粋」という美学を大事に持って生きる方が収まりが良いのではないかと思います。
もともと、多くの日本人はその価値観に重きを置いて生きてきたわけですし。
私たち日本人は誰しも潜在的に「粋」なことに惹かれますから、そうすることできっと周囲からも一目置かれる存在になることでしょう。
ただし、周囲に「粋」なことを過剰にアピールしたり、「粋」を追求して必死になりすぎると、それはそれで「野暮」になってしまうので、その塩梅(あんばい)が難しいところです…。
最後に
以上、ここまで日本人なら誰しもが持っている「粋」という美意識を持って生きるということについて書いてきました。
それは、日本人にとっては古くて新しい、そして美しい生き様です。
あなたもぜひ「粋」な人生を歩んでください。
きっと艶っぽくなりますよ。

私も今日からいきなり「粋」に生きる!
 このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。
このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者はこうの ひろゆき(パーソナルコーチ)。
→もっと見る | 仕事依頼
Follow
メールマガジン
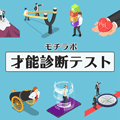 才能診断テスト
才能診断テスト
あなたの才能が「見える化」される。全世界で2000万人以上が受けた才能診断ツールをベースにした本格派。 私の本が出版されました!!
私の本が出版されました!!
9割の人は自分の”心の使い方”を知らないために人生損しています。